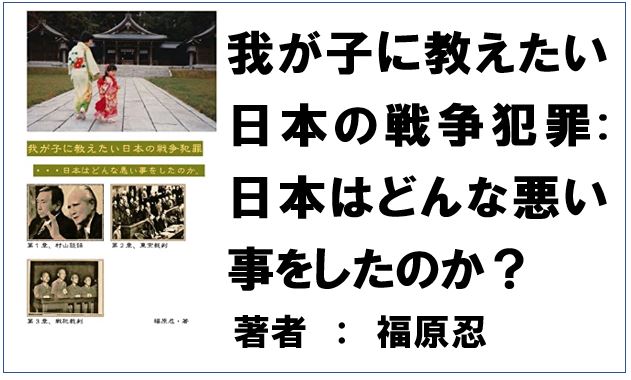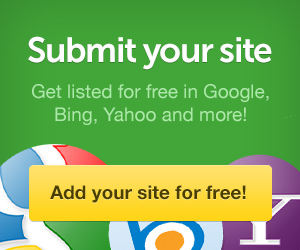辛亥革命6ー満漢南北戦争の推移
南部における孫文の民族独立革命による「中華民国」樹立、北部における袁世凱の帝政終焉による「北京共和政府」の樹立、歴史上「辛亥革命」と呼ばれる、中国の南北に夫々おける政治変革の時期を経て、中国では、満州民族を主体とする北部の「北京政府」と、漢民族を主体とする南部の「南京政府」の2つに、国家が大きく分裂する事態が生じました。
満州民族を主体とする北部の「北京政府」では、袁世凱が急死したのち、袁世凱が率いていた「北洋軍閥」という派閥が分裂し、奉天派(ほうてんは)、直隷派(ちょくぞくは)、安徽派(あんきは)、山西派(さんせいは)の大きく4つの派閥(軍閥)に分裂しました。
| 派閥名 | 代表人物 | 出身地 |
| 直隷派 | 馮玉祥(ふう ぎょくしょう) | 直隷省(黄河下流の北部地域) |
| 奉天派 | 張作霖(ちょうさくりん) | 奉天省(中国東北部ー満州地域) |
| 安徽派 | 段 祺瑞(だん きずい) | 安徽省(中国中部の東北地域) |
| 山西派 | 閻錫山(えん しゃくざん) 傅作義(ふ さくぎ) |
山西省(中国北部の平野地域) |
上記の4つの派閥の代表人物は、辛亥革命時代の袁世凱の後継者であり、第2世代といえる人物といえるでしょう。この4つの派閥(軍閥)が、連合や分裂を繰返しつつ、北部での内乱状態に陥ります。日本やその他の国々が、どこの派閥を支援し、どこがどう勝ったか経緯は全て省きます。
1916年袁世凱の急死した後、1924年までは直隷派が「北京政府」の主導権を握っていたようです。1924年は、直隷派であった馮玉祥が、直隷派を離脱し「北京政変」と呼ばれる軍事クーデターを起こします。これは清国皇帝が紫禁城を追放されることになった軍事クーデターでした。
馮玉祥は元々は「北京政府」側の人間であり、南部の孫文や蒋介石とは対立する関係でした。しかし、「北京政府」という共和政府は成立したものの、清国の朝廷は依然として北京に存在する(清国が終焉していない)状況でした。1912年の辛亥革命より12年の歳月が流れ、清国の皇帝(天皇)も18歳となっていました。こうした状況であれば、清国で帝政を復活させようとする一派が台頭して来るのも、歴史では良くある話でしょう。
そこで、馮玉祥が軍事クーデターを起こし、1924年10月23日、清国を皇帝(天皇)を居城から退去させ、朝廷も含め国家として完全に終焉に追い込んだといえます。また、この時、馮玉祥は「北京政府」側から完全離脱し、南部の蒋介石の「南京政府」側へ寝返ったようです。
「北京政府」では混乱が生じたものの、安徽派の段祺瑞を臨時執政として再建を図ります。この時、満州奉天出身であり、奉天派の代表であった張作霖は、「南京政府」へ寝返った馮玉祥とは対立構造が生じたといえます。本来であれば、張作霖が「北京政府」の代表になるところだったと思われますが、この頃は既に南北での軍事衝突が発生しており、張作霖は北部の軍隊を率いて南部政府軍に抗戦する必要性から、内閣の執政職務に就かなかったのかも知れません。
1924年9月から、孫文は「北伐」を企画していたようです。それに合わせ、馮玉祥が北京で軍事クーデターを起こし、清国を完全終焉させ、北部政府の混乱に乗じ、南部の孫文を中心に南北統一政府の樹立に持って行こうとしたと考えます。しかし、肝心の孫文は北京入りしたものの、ガンで療養中であり、翌年1925年3月には北京で死去します。
南京では、蒋介石が孫文の死を受け、孫文の正当な後継者として、孫文の政権基盤を引き継ごうと動き出します。私が「基礎編ー中国民主革命での主要人物」で述べた様に、孫文は1866年生まれの第1世代といえます。蒋介石は1887年生まれの第2世代。汪兆銘は1883年生まれ。毛沢東は少し年下で1893年生まれです。1925年3月に孫文が死去した後は、年代的にも、蒋介石と汪兆銘が対立する構造になりました。
しかし、この当時は、孫文の側近として、廖 仲愷(りょう ちゅうがい)という人物がいました。1877年生まれです。また、もう一人、胡漢民(こ かんみん)という人物も重要な地位についていました。こちらは1879年生まれです。前者の廖仲愷は、共産主義に理解の深い人物でした。孫文が起こした南部政府は常に北部の北京政府と対立構造にありました。北部の北京政府は共和制であり、中国の共産主義化には反対の立場であり、必然的に、共産党や共産主義者に対しては厳しい対応(処刑)などを行っていました。「敵の敵は味方」の理論で、この時期、共産党と孫文の率いる南部民主政府(中国国民党)が「同盟=1924年第一次国共合作」を結んでいますが、これが理由でしょう。同盟して北部政府へ対抗したのです。そして、孫文の側近の廖仲愷が共産党との「仲介役」となっていました。
ところが、1925年3月に孫文が亡くなると、蒋介石は、まず、この廖仲愷と対立を深めて行きます。これは蒋介石が軍隊を掌握するに当たり、イギリスを後ろ盾としていた事が大きな理由でしょう。イギリスとロシア(ソビエト)は対立構造があります。イギリスの植民地化政策と、ロシア(ソビエト)の共産主義は完全に相容れないといえます。そのため、蒋介石は、まず、共産党とのパイプ役となっていた廖仲愷の暗殺を謀ります。廖仲愷の暗殺は1925年8月でした。これは蒋介石以外に犯人は有得ないといえますが、当時、孫文の南部政府(広東政府)で、胡漢民は大元帥代理を務めていたため、蒋介石はこちらの人物も排斥するため、犯人を胡漢民だとして失脚に追い込みます。胡漢民は、共産党とのパイプ役であった廖仲愷を暗殺した犯人にも関わらず、失脚後、1925年9月には、共産主義のロシア(ソビエト)に亡命(逃亡)したようです。蒋介石派イギリスが後ろ盾ですので、胡漢民はイギリスと対立するロシアへ支援を求めたということでしょう。帰国後は、基本的に、蒋介石と対立する汪兆銘の方の勢力に参加していました。
蒋介石は、その後も、孫文の南部政府(広東政府)の全政治基盤を、「正当な後継者」として引継ごうと工作を繰返しました。孫文の片腕とまで言われた廖 仲愷は8月に暗殺。孫文死後、大元帥代理を務めた胡漢民は9月には国外追放。当然の流れですが、それ以外の孫文の側近や政府要人(中国同盟会以来の古参の政府要人)などは、軍事学校の校長でしかなかった蒋介石の台頭には難色を示したでしょう。独裁を目論む蒋介石からすれば、こうした人々は完全に排斥する必要があったといえます。
そこで、そうした政府要人が、蒋介石の独裁を危惧し、1925年11月23日、孫文の棺が仮安置されていた北京郊外の西山(碧雲寺)へ集まり、今後の政府方針についての話合い(西山会議)に臨んだのを契機に、それを反政府密談として、1926年1月、中国国民党第二回全国代表大会で、全員を弾圧し、永久党籍剥奪などの処分を下し、孫文の継承政府から排斥します。
その後、孫文の後継者として周囲からも認められていた汪兆銘については、1926年3月20日、蒋介石は、広州で中山艦事件(ちゅうざんかんじけん)という軍事クーデターを起こし、共産党員の大量弾圧を決行しましたが、広州は、汪兆銘が主席を務める政府所在地でした。共産主義のロシア(ソビエト)にとっては、中国南部政府(広州政府)に対して、その責任を追及する事態と言えます。こうした場合は、首相辞任や国家主席退任し、対外的に謝罪の意を表すのは常套手段です。当時は、汪兆銘が政府主席でしたので、汪兆銘が責任を取って辞任に追い込まれたといえます。蒋介石は、当然、これを見越して、中山艦事件(ちゅうざんかんじけん)を起こしたのです。
蒋介石の人間性からすれば、前年の廖仲愷の暗殺と同様、汪兆銘の暗殺を企画するのは目に見えています。そこで、汪兆銘は、1926年3月、中国を離れ、フランスへ家族(妻)を連れて亡命(逃亡)したのです。現在の歴史では「外遊」とされていますが、これは暗殺の危機を回避するために国外逃亡とするのが状況的に正しいでしょう。
こうした政府要人の排斥工作を経て、1926年4月16日、蒋介石は、蔣介石は国民政府軍事委員会主席の地位に就きます。そして、孫文の正当な後継者であることを、国内外に宣言する意味も込めて、1926年7月より、「亡き孫文の意志を継いで」という名目で、「北伐」を開始しました。
当然、この「北伐」には、イギリスが背後で手厚い軍事支援を行っていたから踏み切れた軍事侵攻です。イギリスは、中国の植民地化を目論んでいた国です。なぜ北部へ軍事侵攻を望んだのかは、中国では、中南部は広大な平野地帯であり、主な産業は農業や手工業であるのに対し、満州地区のある東北部、蒙古モンゴルなどの北部は、鉄鉱石や石炭や原油などの豊富な産地であり、イギリスにとっては何としても手に入れない地域だったからです。
また、これは日本が満州国と密接な関係にあった理由でもあります。日本は、現在の国際協力プロジェクトと同様に、満州国や満州地域にとっては、優良かつ最大の輸出先であると同時に、鉄道網や鉱山などの開発、インフラ整備資金の借款などを行う「経済協力パートナー」であったのです。もちろん、更に西方のロシア(ソビエト)にとっても、それは同様であり、ロシア(ソビエト)の天然資源の主要輸出先となっていました。日清戦争、日露戦争を経て、日本に満州鉄道の権益や周辺地域の開発権を与えたのも、最終的には、これが理由でした。蒋介石もイギリスも、この日本が保有する権益を奪うために、「北伐」という軍事侵攻を行わざるを得なかったのです。