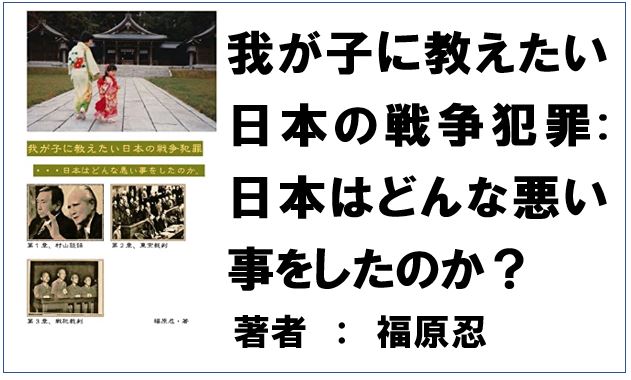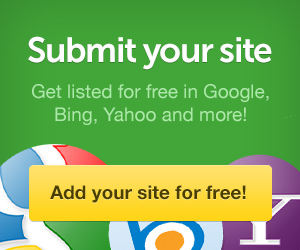北伐の真相1ー第一次支那動乱
支那動乱とは、蒋介石の「北伐宣言」に伴って起きた中国での南北政府間での「南北内乱戦争」のことを言います。1926年7月の蒋介石の「北伐宣言」から始まった北伐は、中国を2分する大きな内乱戦争に発展しました。単なる「北伐」ではなく正に「支那動乱」であったといえます。
1926年は、大正15年=昭和元年です。前年の1925年3月に孫文が亡くなると、蒋介石は、まず、南部政府内での中心的地位を得ようと画策を繰返していきます。「北伐」の前段階としてじゃ、蒋介石が南部政府軍を動かせる立場になる必要があったためです。
蒋介石は、孫文が健在であった頃は、黄埔軍官学校(こうほぐんかんがっこう)という士官養成学校で校長を務めていたに過ぎず、南部政府政権の中心とは距離のある地位にいました。しかし孫文の死後、孫文の側近であった人物を次々を失脚させ、時には暗殺し、翌年には孫文の政治軍事基盤を一手に掌握するに至ります。この時点までは、孫文は、イギリスとはある程度は距離を保った関係であったのではと思いますが、ここから蒋介石の軍事基盤掌握により、イギリスとの軍事協力体制が確立して行ったといえます。蒋介石の率いる南部政府軍は、人工的に見れば規模は大きかったといえますが、北部では「清帝国」から続く国家軍隊が既に存在し、袁世凱以後も、北京政府により軍事基盤は継続されていました。ところが、蒋介石の北伐では、南部政府軍が圧倒的に優勢となりました。イギリスからの多大な軍事支援が無ければ、北部政府軍に勝てるはずはありません。
北京政府内の軍閥と北京政変
当時は、北部政府側でも政権闘争での軍事衝突が起きていたようです。これは、満州民族を主体とする北部の「北京政府」では、袁世凱が急死したのち、袁世凱が率いていた「北洋軍閥」という派閥が分裂し、奉天派(ほうてんは)、直隷派(ちょくぞくは)、安徽派(あんきは)、山西派(さんせいは)の大きく4つの派閥(軍閥)に分裂したためです。
| 派閥名 | 代表人物 | 出身地 |
| 直隷派 | 馮玉祥(ふう ぎょくしょう) | 直隷省(黄河下流の北部地域) |
| 奉天派 | 張作霖(ちょうさくりん) | 奉天省(中国東北部ー満州地域) |
| 安徽派 | 段 祺瑞(だん きずい) | 安徽省(中国中部の東北地域) |
| 山西派 | 閻錫山(えん しゃくざん) 傅作義(ふ さくぎ) |
山西省(中国北部の平野地域) |
1924年10月23日の「北京政変」では、南部政府軍との関係が深かめた馮玉祥(ふう ぎょくしょう)が、孫文に働き掛け、平和的な南北政府の統一への道を模索したのではと考えます。そこで北京で軍事クーデターを起こし、北部の北京政府から「清国の朝廷」を排除しようとしたといえます。「清国の朝廷」の存在は、南部の民主革命派とは相容れないからです。
孫文は、この馮玉祥の呼びかけを受け、北京を訪れています。ここで平和的な南北統一政府の樹立に向けて、南北両政府間での交渉が行われる予定だったのでは無いでしょうか。しかしながら、孫文は、半年後の1925年3月に、北京で病死してしまいます。これは歴史上は、ガンで死亡したことになっていますが、前年、日本で講演を行っているなど、ガンで闘病していた人物の行動としては若干不可解ですので、もしかすると、蒋介石の指示、又は、平和的な南北政府統一を阻止しようとする一派による「暗殺」だった可能性は否定できないでしょう。
結果、この時点での南北間政府交渉は決裂してしまいます。その後、北京で孫文の亡骸を安置していた寺で、側近や政府関係者が事後について会談を開いたものの、蒋介石に「反政府密談」とされ、弾圧を受け、殆どの側近が失脚したため、平和的な交渉の方向からは逸脱したといえます。孫文の後継者とされた汪兆銘も、蒋介石の迫害に遭い、1926年3月にはフランスへ逃亡する事態となりました。結果、北部を軍事制圧し、南部の完全支配下に組み入れる形での、南北政府統一を行おうとする蒋介石を止める勢力が無くなる状態となり、この機に便乗して、1926年7月に、蒋介石が「北伐を宣言」=「北部政府への宣戦布告」を行うに至りました。
この「北伐」=「支那動乱」=「中国南北戦争」は、植民地化政策の5段階でいうと、第3段階後半、内乱勃発で王朝を滅亡させ、求心勢力を潰したところで、さらに国内での内乱紛争を勃発させる。中国は、領土が広大であり、当時の「清の王朝」は征服王朝であったことから、国家政権争いに加え、漢民族の独立紛争の様相も加わっていました。しかし、北部政府の直隷派だった馮玉祥(ふう ぎょくしょう)が、南部の蒋介石側に寝返り、「北京政変」という軍事クーデターにより「清の朝廷」を滅亡させた上で、国を南北に大きく分ける様な内乱の勃発に至っております。
既に植民地化したベトナムやビルマに近い南部地域からは、揚子江、黄河の中国2つの大河を隔てた北側に位置する北京政府には、イギリスやフランスなどの影響はある程度抑えられたといえます。また、早い段階で、多分、明治維新の更に以前から、清帝国と日本は、ヨーロッパ諸国の植民地化には警戒し、水面下での情報交換など協力体制は取っていたでしょう。1912年に清は帝国としては滅亡していますが、王朝としては継続していたと言えますので、明治維新により、当時のアジアで唯一、ヨーロッパ諸国による植民地化危機を脱した日本には、支援を求めたのは当然の流れと言えます。
明治維新の直後、1894年から1895年に掛けて起きた日清戦争での勝利により、日本は、ヨーロッパ諸国と並び、中国本土での領土問題に関与する立場になったといえます。日本は主に、満州東北部などからの天然資源の獲得が目的であり、現在の様の国際協力プロジェクトの様に、資金借款と人材や技術提供を行い、石油や石炭や鉄鉱石などの天然資源を優先輸入するという「ビジネス」を展開し、その「ビジネス」が問題無く進められれば、中国で敢えて「戦争」などする理由もありませんでした。
しかしながら、蒋介石が半ば強引に起こした「北伐」=「支那動乱」=「中国南北戦争」の際、蒋介石は、北部政府と経済軍事支援体制(同盟関係)にあった日本に対しては、在留日本人への虐殺や強奪などを行っていたため、日本としては、本土から、大規模な軍隊を派遣せざるを得ない状況に陥ったといえます。蒋介石の日本への残忍な無差別攻撃を行った背景としては、北部政府と日本がそれだけ経済関係や軍事関係などで非常に親密な関係にあったからといえるでしょう。
尚、当時発行の「歴史写真」では、虐殺や爆殺や強奪などは「事件」、それより広範囲での軍事衝突を「事変」、更に政府レベルでの軍事衝突を「動乱」と表現しているようです。この支那動乱は、一般的には「北伐」という呼び方が主流のようです。しかし、「北伐」とは南側の国が北側を討伐するという意味ですので、世界史的には当時日本が使っていた「支那動乱」とう表現の方が正しいと思います。